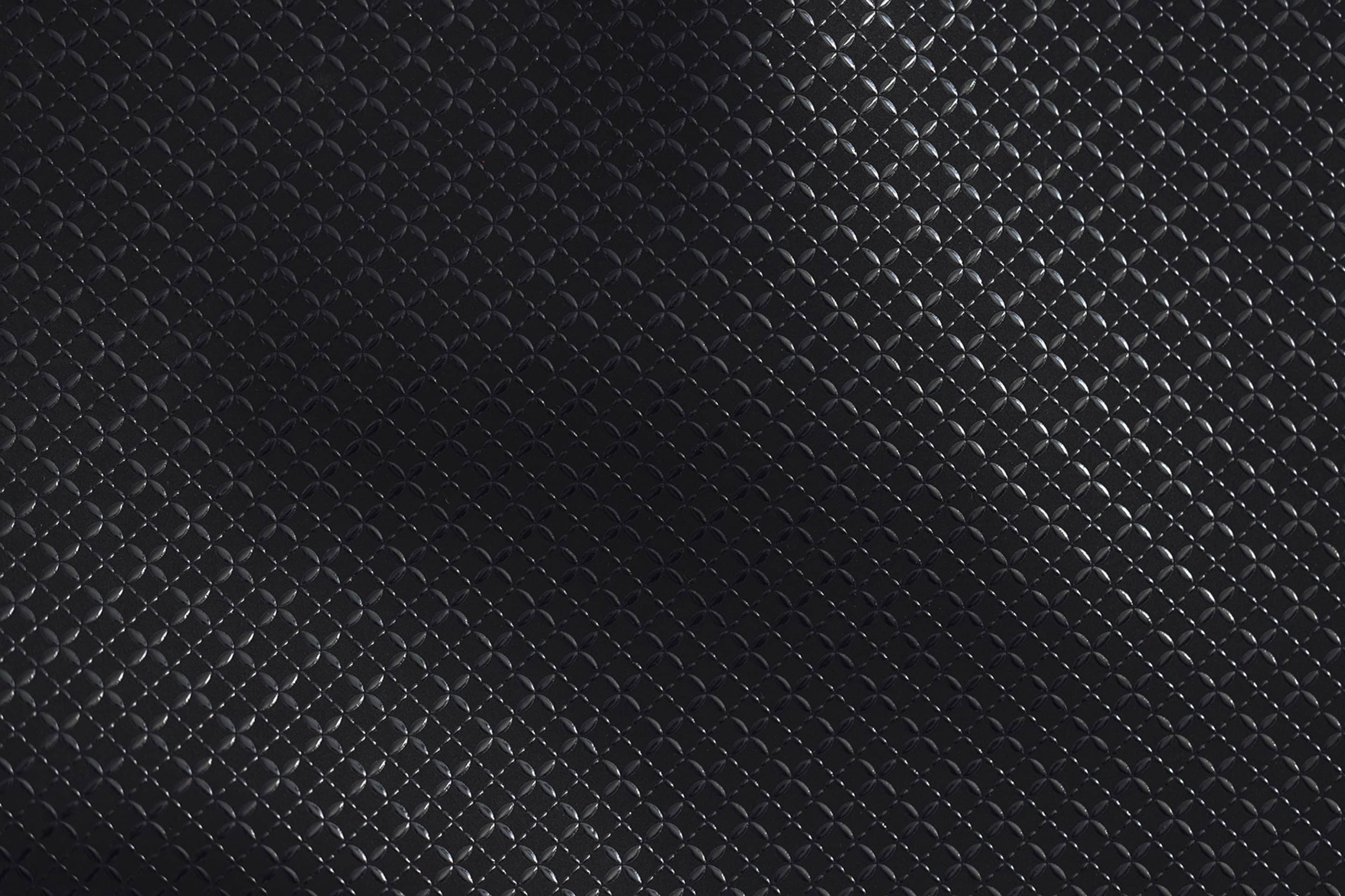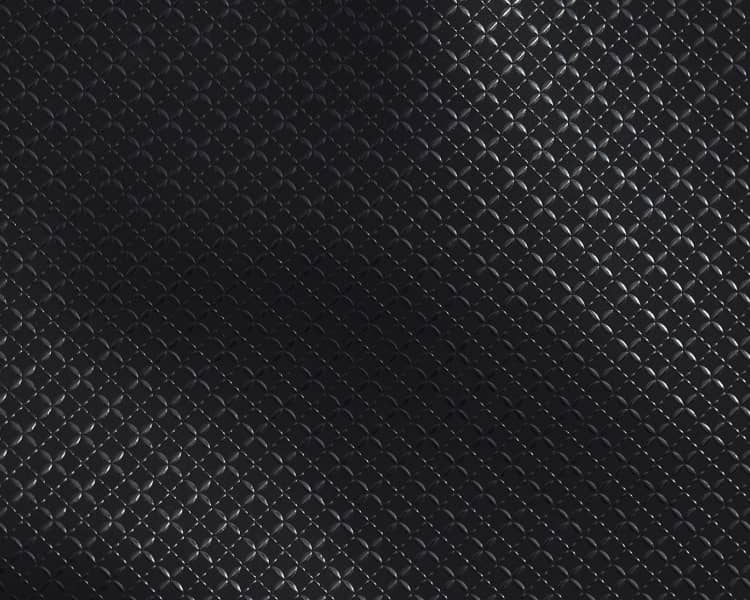季節をつぶさに感じ、
生まれた春の言葉。
七十二候では雨水の次侯を
「霞始靆(かすみはじめてたなびく)」といいます。
雨や雪解け水の水蒸気、塵などで
この季節は空に霞がかかる日が多くなります。
「春霞」は季語になっており、朝霞や夕霞、薄霞、
遠霞、八重霞などの言葉も生まれました。
夜に霞がかかっていても、それは霞とはいわず、
「朧(おぼろ)」と呼ぶのだそうです。
その時々にふさわしい形容のしかたがある日本語は、
あらためて美しいものだと思い直しました。
今は、どんな霞がたなびいているでしょうか。